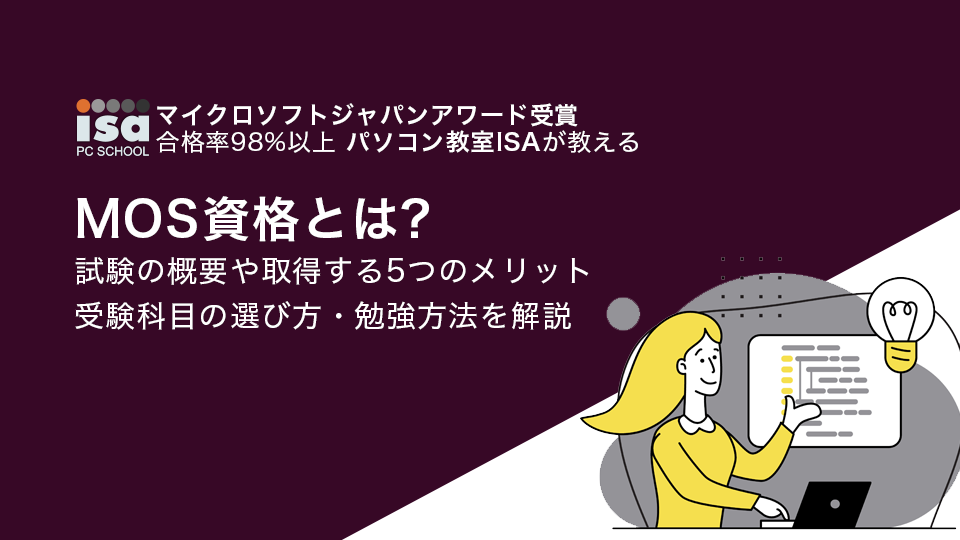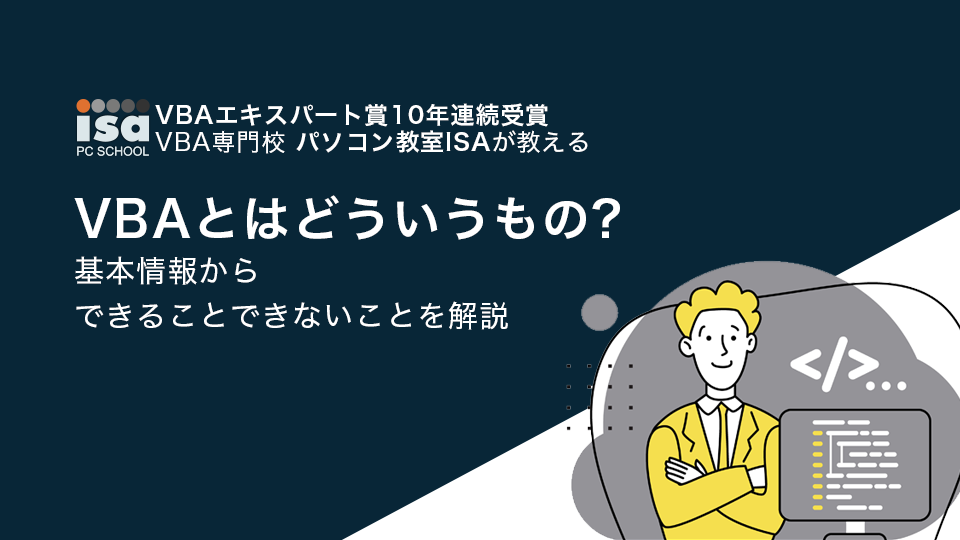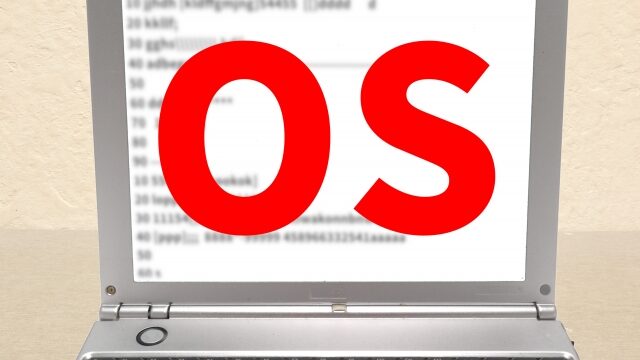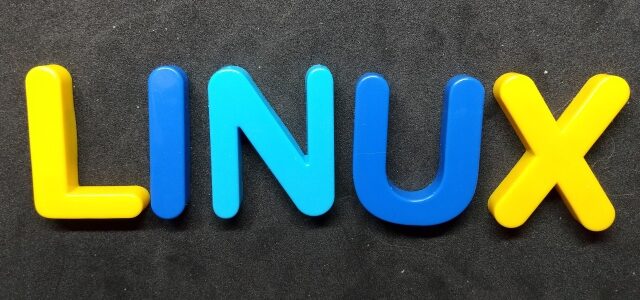「パソコン教室ISA」ライターチームです。
Linuxを始めたいけれど、インストール方法がわからない人も多いのではないでしょうか。本記事では、Linuxの基本知識からインストール手順、注意点まで詳しく解説します。初心者の人でも安心してLinuxを始められるよう、わかりやすく説明するので、ぜひ最後まで読んでください。
ISA ITスクールの詳細はこちら
Linuxをインストールする前に押さえたい知識
Linuxをインストールする前に、基本的な知識を押さえておくことが重要です。Linuxとは何か、ディストリビューションの概念など、核となる情報を理解しておくと、インストール作業がスムーズに進みます。ここでは、これらの基礎知識について詳しく説明します。
Linuxとは
Linuxは、オープンソースのオペレーティングシステム(OS)です。1991年にリーナス・トーバルズによって開発が始まり、現在では世界中で広く使用されています。無料で利用でき、ユーザーが自由にカスタマイズできる点が特徴です。
サーバーやスマートフォン、組み込み機器など、さまざまな場面で利用されており、安定性や柔軟性に優れています。また、初心者の人にも使いやすいGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)を備えている点も特徴です。
ディストリビューションとは
ディストリビューションは、Linuxカーネルと他のソフトウェアを組み合わせてパッケージ化したものです。Ubuntu、Fedora、CentOS、Debian、Linux Mintなど、さまざまな種類があります。
各ディストリビューションには特徴があり、例えばAlmaLinuxはCentOSの後継として開発され、サーバー用途に適しています。初心者の人には使いやすさと豊富な日本語情報が特徴のUbuntuがおすすめです。自分の目的や経験レベルに合わせて、適切なディストリビューションを選ぶことが重要です。
パソコン教室ISAの体験授業で自分にあったレベルを相談してみる
Linuxのインストールには仮想環境がおすすめ!
Linuxを始めるなら、仮想環境を利用するのが初心者にも安全で効率的です。仮想環境を使えば、既存のOSに影響を与えることなく、Linuxを簡単に試すことができます。
仮想環境とは
仮想環境とは、1台のコンピューター内に仮想的に作られた別のコンピューター環境のことです。物理的なハードウェアを論理的に分割し、複数のOSを同時に動作させることができます。WindowsやmacOS上でLinuxを動かすことが可能で、メインのOSに影響を与えずに安全に学習やテストをおこなうことが可能です。
CCNAとLPICどちらの資格を取るべき?IT系資格の資料をダウンロード
パソコンスクールISA
Office・IT・プログラミング等の
パソコンスキルアップを徹底サポート!
東京、横浜、埼玉、千葉の
最寄駅5分以内!オンライン授業も
Linuxインストールの手順
Linuxをインストールする方法はおもに2つあります。仮想環境を使う方法とUSBメモリを使う方法です。ここでは、それぞれの手順を詳しく説明します。
仮想環境を使う方法
仮想環境を導入するには、まずVirtualBoxなどの仮想化ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。公式サイトから最新版を入手し、画面の指示に従ってセットアップを行いましょう。
インストールが完了したら、仮想マシンを新規作成します。メモリサイズやストレージ容量を設定し、仮想ハードディスクを作成します。これで、Linuxをインストールする準備は完了です。
Ubuntuのダウンロード
次に、UbuntuのISOイメージファイルをダウンロードします。Ubuntu公式サイトにアクセスし、最新のLTS(Long Term Support)バージョンを選択しましょう。ダウンロードには時間がかかる場合があるので、安定したインターネット接続環境で行うことをおすすめします。
仮想環境にUbuntuのインストール
仮想環境にUbuntuをインストールするには、まず仮想マシンを起動し、ダウンロードしたISOイメージを選択します。インストーラーが起動したら、言語設定やキーボードレイアウトを選択し、インストールタイプを決定します。
次にパーティションの設定を行い、ユーザー情報を入力します。インストールが完了したら、再起動して仮想環境でUbuntuが正常に動作することを確認します。これで、仮想環境の構築は完了です。
USBメモリを使う方法
USBメモリでLinuxをインストールするには、まずRufusなどのツールでブータブルUSBを作成します。次に、BIOS設定でUSBからの起動を優先し、USBからブートします。インストーラーの指示に従ってUbuntuをインストールし、パーティションの設定やユーザー情報の入力を行います。最後に、USBを取り外し、インストールしたLinuxが正常に起動するか確認します。
\ IT系講座の詳しい情報を受け取る /
Linuxインストールができないときに確認すること
Linuxのインストールに失敗する原因はいくつかあります。ここでは、主な3つのポイントを確認し、トラブルシューティングを行う方法を解説します。
ストレージの空き容量があるか
Linuxをインストールする際は、十分なストレージ容量が必要です。dfコマンドを使用して、現在のディスク使用状況を確認しましょう。一般的に、Linuxのインストールには最低8GB程度の空き容量が必要です。容量が不足している場合は、不要なファイルを削除するか、より大容量のストレージに交換しましょう。
動作環境がLinuxに対応しているか
使用しているパソコンがLinuxの動作環境に対応しているかを確認しましょう。CPUやメモリ、グラフィックカードなどのハードウェアスペックが、インストールしようとしているLinuxディストリビューションの要件を満たしているか確認します。また、UEFIやBIOSの設定が適切であるかも重要です。互換性に問題がある場合は、別のディストリビューションを試すか、ハードウェアのアップグレードを検討してください。
パソコンに異常がないか
インストールの失敗は、パソコン自体の問題が原因となっている可能性もあります。ハードウェアの不具合や、故障した部品がインストールを妨げている場合があるでしょう。
ハードウェア接続や冷却ファンの動作を確認し、メモリやハードディスクなどのコンポーネントに異常がないか診断ツールを使用してチェックしましょう。問題が見つかった場合は、該当する部品の修理や交換が必要になる場合があります。
パソコン教室ISAの体験授業で自分にあったレベルを相談してみる
\ IT系講座の詳しい情報を受け取る /
Linuxをインストールする際の注意点
Linuxをインストールする際は、いくつか重要な注意点があります。これらを事前に把握することで、スムーズなインストールを実現しましょう。
通信制限がある
Linuxのインストールには、大容量のデータ通信が必要です。ディストリビューションのISOファイルは数GBに及ぶため、ダウンロードには時間がかかります。また、インストール後のアップデートにも大量の通信が発生します。
そのため、通信量に制限のある環境では注意が必要です。可能であれば、制限のないWi-Fi環境でのインストールをおすすめします。
データ消失のリスクがある
Linuxをインストールする際、誤った操作によってハードディスク内の既存データが消失するリスクがあります。特に、デュアルブートを設定する場合や、パーティションを手動で設定する際には細心の注意が必要です。
また、重要なデータは必ずバックアップを取っておくことが大切です。初心者の人は仮想環境でのインストールから始めることをおすすめします。
動作がスムーズなパソコンで行う
Linuxは比較的軽量なOSですが、快適に使用するにはある程度のスペックが必要です。特に、グラフィカルな環境を利用する場合は、CPUやメモリ、グラフィックカードの性能が重要です。
Linuxは古いパソコンでも動作します。しかし、レスポンスの遅さやフリーズなどのストレスを避けるためにも、可能な限り性能の良いパソコンでインストールすることをおすすめします。
ディストリビュージョンは日本語情報が多いものを選ぶ
Linuxの世界では英語の情報が圧倒的に多いので、初心者の人は日本語の情報が豊富なディストリビューションを選ぶことが重要です。その点、UbuntuやLinux Mintなどは、日本語のドキュメントやコミュニティが充実しています。トラブルシューティングや設定変更の際は、これらのように母国語で情報を得られる方が、スムーズに解決できます。
Linuxをより便利に使うための設定
Linuxをインストールした後は、快適に使用するための設定が重要です。ここでは、デスクトップサイズの調整、コピー&ペースト機能の共有、共通フォルダの作成、3つの設定について解説します。
デスクトップサイズを全画面にする
Linuxのデスクトップを全画面表示にすることで、作業効率が向上します。Ubuntuなどのディストリビューションでは、「設定」から「ディスプレイ」を開き、解像度を調整できます。
VirtualBoxを使用している場合は、「デバイス」メニューから「Guest Additions CD イメージの挿入」を選択し、インストールすることで画面の自動リサイズが可能になります。
Linuxとのコピー&ペースト機能を共有する
ホストOSとLinux間でのコピー&ペーストを可能にすると、作業がスムーズになります。VirtualBoxの場合、「設定」から「一般」を選択し、「高度」タブで「クリップボードの共有」を「双方向」に設定します。
VMwareを使用している場合は、「VMware Tools」をインストールし、「オプション」タブで「コピーアンドペースト」を有効にしましょう。
Linuxとの共通のフォルダを作成する
ホストOSとLinux間でファイルを共有するには、共通フォルダの設定が便利です。VirtualBoxでは、「設定」から「共有フォルダ」を開き、新規共有フォルダを追加します。「自動マウント」にチェックを入れ、「OK」をクリックしてください。
Linux側では「mkdir」コマンドを使用して共有フォルダをマウントポイントとして作成し、「mount」コマンドでマウントします。
本記事では、Linuxの基本知識から具体的なインストール手順、そして便利な設定方法まで解説しました。Linuxのインストールは、初心者の人でも適切な手順を踏めば十分に実行可能です。
仮想環境を利用すれば、既存のOSに影響を与えることなく安全にLinuxを試すことができます。また、Ubuntuなどの初心者向けディストリビューションを選び、十分な空き容量があるパソコンで作業を行うこともポイントです。
このように、パソコン操作は目的に合った適切な手順を踏めば、初心者の方でも決して難しくありません。もしもLinuxを本格的に学びたい、パソコンスキルを身につけたいとお思いなら、プロの講師から学んでみませんか?
弊社が運営するISA ITスクールは、Microsoftジャパンが1年に1社えらぶLearning Awardをここ10年で3度受賞しています。ITスキルを磨きたいとお考えの方は、この機会にぜひISA ITスクールの受講を検討しご希望のスキルを身につけてみませんか?
ISA ITスクールの詳細はこちら